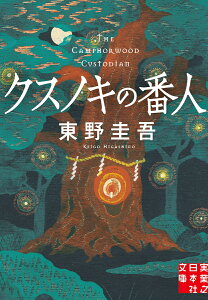『spring』とは
本書『spring』は、2024年3月に筑摩書房から448頁のハードカバーで刊行された、長編のバレエ小説です。
『蜜蜂と遠雷』でピアノコンクールを舞台とした作品で私たちを驚かせてくれた作者が、今度はバレエという踊りをテーマに新たな驚きを見せてくれました。
『spring』の簡単なあらすじ
構想・執筆10年ーー
稀代のストーリーテラーが辿り着いた最高到達点=バレエ小説
「俺は世界を戦慄せしめているか?」自らの名に無数の季節を抱く無二の舞踊家にして振付家の萬春(よろず・はる)。
少年は八歳でバレエに出会い、十五歳で海を渡った。
同時代に巡り合う、踊る者 作る者 見る者 奏でる者ーー
それぞれの情熱がぶつかりあい、交錯する中で彼の肖像が浮かび上がっていく。
舞踊の「神」を追い求めた一人の天才をめぐる傑作長編小説。史上初の直木賞&本屋大賞をW受賞した『蜜蜂と遠雷』や演劇主題の『チョコレートコスモス』など、
表現者を描いた作品で多くの読者の心を掴みつづける恩田陸の新たな代表作、誕生!
ページをめくるとダンサーが踊りだす「パラパラ漫画」付き(電子版には収録なし)(内容紹介(出版社より))
『spring』の感想
本書『spring』は、直木賞と本屋大賞を同時受賞した『蜜蜂と遠雷』という音楽をテーマにした作品で私たちを驚かせてくれた作者恩田陸が、新たにバレエをテーマに紡ぎだした長編のバレエ小説です。
今回も作者の筆の冴えは見事であり、四百頁を軽く超える濃密な作品ではありましたが、最後まで緊張感が途切れることなく読み終えることができました。
本書は天才的ダンサーであり振付師の萬春(よろずはる)という人物を、章別に異なる視点から描き出している全四章からなる作品です。
「第一章 跳ねる」の語り手は深津純というダンサーです。
純にとって春はワークショップで一人だけ輝きが異なる特別な存在として意識した人物であり、春の振付師としての可能性を意識させた人物でもあります。
「第二章 芽吹く」の語り手は春の叔父さんの稔さんです。
春の人となりを、春の幼いころからを知っている身内ならではの観察眼で掘り下げています。
「第三章 湧き出す」は滝澤姉妹の妹の七瀬です。
春によれば、姉の美潮のバレエは「正しすぎる」のですが、七瀬は「ちょっと面白い」のであり、七瀬には頭の中で別な音楽が流れていると言います。その頭の中で鳴っている音に忠実に踊りをつけているから外からは余計な踊りに見えるのだと言うのです。
そして「第四章 春になる」の語り手は春自身です。
この章では、これまでの三人とのエピソードが春自身の目線で語られており、物語に厚みが出ています。
作者の恩田陸の表現力の素晴らしさは言うまでもありません。
『蜜蜂と遠雷』ではピアノコンクールでのピアニストの演奏の様子を見事に言語化して直木賞と本屋大賞を同時受賞したその力量は、バレエという踊りの世界を描いても同じように表現してくれているのです。
この作者の文章の表現力の的確さ、その美しさはもちろんのことであり、個人的に驚くのは、春が振り付けをしている多くの踊りが、その全部について恩田陸という作家が実際に脳内でイメージして振り付けされていることです。
例えば、ラベルのボレロという曲に合わせた振り付けのアイデアでは、二頁弱にわたりオーケストラの個々の楽器それぞれに踊り子を割り当てた振り付けを説明してあります。
このようなオーケストラの構成をそのままに使うというアイデアは素人から見ると見事として思えないのですが、実際のダンサーはこのような振り付けを見てどう思うのでしょうか。話を聞いてみたいものです。
ほかにも、私が聞いたこともないドイツのメルヒェン(昔話)をテーマにした振り付けなど、挙げていけばキリがありません。
その振付がバレエの専門家から見てどう評価されるのかはわかりません。
でも、バレエのことなど全く分からない素人からすると、仮にそうした振り付け作業が専門的にはおかしいものだとしても、その振付の表現に隠された作者の知識量は考えるだけでも恐ろしくなります。
元となる音楽だったり民話に関する詳細な知識があって初めてきっかけがあり、その材料をもとに詳細に調べ上げ、その上でバレエに対する感性をもって振り付けをしていく作業がどれだけ大変なことか。
そうした作者の情報量とその情報を生かす能力の高さは私達一般人の想像すらできないところにあると思われます。
そして、春が出会い、影響を受けたバレエの先生たちの森尾つかさやエリックとリシャール、そしてジャン・ジャメなどとの関係性も素晴らしいものがあります。
さらに深津純やハッサン、ヴァネッサ、滝澤姉妹などの友人たちがいて今の春がいます。
加えて、第二章で語り手となった春の叔父さんの稔さんも忘れることはできません。
踊りの表現もさることながら、彼ら相互のつながりの深さ、影響し合い成長していくさまが表現されている本書はまた青春小説であり、成長小説でもあると思えます。
芸術的な感動を小説を読んでいて感じるという経験はそうはできないと思います。本書はその数少ない経験を感じさせてくれる作品だと思うのです。
ちなみに、『チョコレートコスモス』という作品では「演劇」の世界を展開しているそうですが、私はまだ読んでいませんので、そのうちに読みたいと思います。
また、本書の各ページの下部にはダンサーのパラパラ影絵が描き出してあるのも遊び心があり楽しいものです。