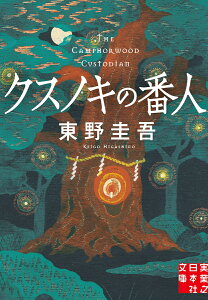『イコン』とは
本書『イコン 新装版』は『安積班シリーズ』の第5弾で、1995年10月に四六判で刊行されて、2016年11月に文芸評論家の関口苑生の解説まで入れて505頁の新装版として講談社文庫から出版された長編の警察小説です。
インターネット全盛の現代からするとかなり古さを感じるパソコン通信の世界を取り上げ、アイドルとは何かまで考察されている珍しい警察小説です。
『イコン』の簡単なあらすじ
「十七歳ですよ。死んじゃいけない」連続少年殺人の深層に存在した壮絶な真実とは!?熱狂的人気を集めるも正体は明かされないアイドルのライブでの殺人事件。被害者を含め現場にいた複数の少年と少女一人は過去に同じ中学の生徒だった。警視庁少年課・宇津木と神南署・安積警部補は捜査の過程で社会と若者たちの変貌に直面しつつ、隠された驚愕の真相に到達する。『蓬莱』に続く長編警察小説。
「十七歳ですよ。死んじゃいけない」
連続少年殺人の深層に存在した壮絶な真実とは!?世紀末”日本”が軋(きし)む。
バーチャルアイドルの影に隠されたものは?
傷つけあう”未成年”の衝撃のリアル!
警視庁少年課・宇津木と神南署・安積警部補が動く!
『蓬莱』続編ともいうべき今野敏警察小説の源流。熱狂的人気を集めるも正体は明かされないアイドルのライブでの殺人事件。被害者を含め現場にいた複数の少年と少女一人は過去に同じ中学の生徒だった。警視庁少年課・宇津木と神南署・安積(あづみ)警部補は捜査の過程で社会と若者たちの変貌に直面しつつ、隠された驚愕の真相に到達する。『蓬莱(ほうらい)』に続く長編警察小説。(内容紹介(出版社より))
『イコン』の感想
本書『イコン』は、『安積班シリーズ』の第五弾作品ですが、細かに見るとシリーズ内の初期三作品「ベイエリア分署」時代に続く「神南署」時代の第二弾作品でもあります。
ただ、本書での安積警部補はどちらかというと脇役に近い存在であり、『安積班シリーズ』に位置付けていいのかは疑問がないわけではありません。
この点、「神南署」時代の第一弾作品『蓬莱』という作品も同様に安積警部補の物語というよりは「蓬莱」というゲームの話を借りた「日本」という国の成り立ちを考察した作品となっていますが、一応は安積警部補の物語とはなっています。
しかしながら、『蓬莱』も含めて『安積班シリーズ』とするのが一般的なようですので、本稿でもそのような位置付けとしています。
本書『イコン』はそのパソコン通信上で人気となっているアイドルの有森恵美をめぐり起こった殺人事件について、神南警察署刑事課強行犯係の安積剛志警部補が、同期の警視庁生活安全部少年課警部補である宇津木真とともに活躍する警察小説です。
今野敏の作品での少年課に所属している警察官といえば、『警視庁強行犯係・樋口顕シリーズ』に出てくる警視庁生活安全部少年事件課の氏家譲や『鬼龍光一シリーズ』に登場する富野輝彦巡査部長などが思い出されます。
彼ら少年事件課の捜査員たちが重要性を持って描かれているのは、今野敏という作家の中で少年事件がそれなりに重きが置かれているということなのでしょう。
本書でも、少年らの行動に振り回される安積や宇津木らの姿があります。
情報収集のために有森恵美というアイドルのライブを訪れていた警視庁生活安全部少年課の宇津木真警部補の眼の前で、一人の少年が乱闘騒ぎの中殺されるという事件が発生します。
通報により駆けつけたのが安積警部補らだったのですが、このライブのアイドルの有森成美という存在がパソコン通信の中での存在ということで、宇津木も安積も全く理解ができないのでした。
本書『イコン』では「パソコン通信」が重要なアイテムとして登場していますが、それもそのはずで本書は初版が1995年10月に出版されている三十年近くも前の作品です。
ここで登場する「パソコン通信」とは、モデムというアナログ信号をデジタル信号に相互変換する機器などを介して電話回線を通じてデータを送受信し、基本的にテキストベースで会話をする通信システムで、現在のインターネットの前身と言ってもいいシステムだと思います。
当時はニフティサーブ(NIFTY-Serve、NIFTY SERVE)などが大手の通信会社として利用されていました。
また、今ではパソコンなどで普通に使われているアイコンについても、その由来が宗教画のイコンにあることの説明から為されています。
ただ、個人的にはDOS画面でコマンドベースで行うパソコン通信しか覚えておらず、アイコンでプログラムを立ち上げて行うパソコン通信は知りません。
でも、本書『イコン』で特筆されるべきなのは、作者今野敏による「アイドル論」ではないでしょうか。
妙に説得力のあるアイドル論だと思っていたら、今野敏は上智大学を卒業後、数年間ではあるものの東芝EMIに入社して芸能界に近いところにいたというのですから納得です。
加えて先に述べたパソコン通信に関する知識など、著者の作品は時代を取り込んだものが多いようで、そうしたアンテナもこの作者の人気の原因となっているのでしょう。
『安積班シリーズ』初期作品で安積班のメンバーが勤務する警察署もまだ定まっていない時期の物語であり、またシリーズの中でも異色的な物語ではありますが、やはり今野敏の描く作品としての魅力は十二分に備わった作品です。
異色の作品であるからこその魅力があると言ってもいいかもしれない作品でした。