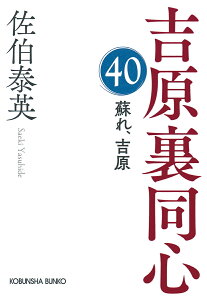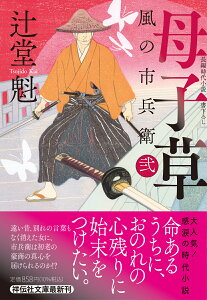『まいまいつぶろ』とは
本書『まいまいつぶろ』は、2023年5月に336頁のハードカバーで幻冬舎から刊行された長編の時代小説です。
第九代将軍徳川家重を描いた作品で、第13回「本屋が選ぶ時代小説大賞」と第12回「日本歴史時代作家協会賞作品賞」を受賞したかなり評価の高い作品です。
『まいまいつぶろ』の簡単なあらすじ
暗愚と疎まれた将軍の、比類なき深謀遠慮に迫る。
口が回らず誰にも言葉が届かない、歩いた後には尿を引きずった跡が残り、
その姿から「まいまいつぶろ(カタツムリ)と呼ばれ馬鹿にされた君主。
第九代将軍・徳川家重。
しかし、幕府の財政状況改善のため宝暦治水工事を命じ、田沼意次を抜擢した男は、本当に暗愚だったのかーー?
廃嫡を噂される若君と後ろ盾のない小姓、二人の孤独な戦いが始まった。(内容紹介(出版社より))
『まいまいつぶろ』の感想
本書『まいまいつぶろ』は第九代将軍の徳川家重と、彼の口となった大岡忠光の生涯を描いた作品で、本屋が選ぶ時代小説大賞と日本歴史時代作家協会賞作品賞を受賞した作品です。
第八代将軍徳川吉宗の嫡子で幼名を長福丸といった徳川家重は、生まれながらの障碍のために口が回らず誰もかれが発した言葉を理解することはできませんでした。
そのうえ彼が歩いた後には尿を引きずった跡が残ったと言われたことから「まいまいつぶろ(カタツムリ)」と呼ばれたそうです。
そうしたことから将軍職にはふさわしくないとも言われましたが、第八代将軍の徳川吉宗の、長子相続こそが将軍職をめぐる争いを防ぐという考えのもと九代将軍に選ばれました。しかし、政の実権は吉宗が大御所として家重の背後にいた、とされています。
本書は、そんな徳川家重の生涯を、家重の側近として生きた大岡兵庫、後の大岡忠光の姿と共に描き出した力作です。
徳川家重という将軍の名は聞いたことがあったものの、本書で描かれているように身体にひどい障害を持っている人物だとは知りませんでした。
ましてや、その家重の言葉を理解できる人物が存在し、その人物が側用人にまで上り詰めたなどという事実もまったく知らなかったのです。
さらに言えば、その人物が大岡忠光という名であり、その人物があの江戸南町奉行として高名な大岡忠相の縁続きの者であることなどもちろん知る筈もありません。
その障害のため、次期将軍としての地位も奪われようとしていた長福丸でしたが、彼の言葉を理解する大岡兵庫が現れたためその人生は全く異なることになります。
ただ、兵庫が長福丸のおそばに上がるについては、兵庫は大岡忠相から長福丸の口として徹しなければならないと言われ、その言を生涯守り抜いたとされているのです。
将軍の言葉を理解できるものが一人しかいないということは、兵庫が将軍の言葉を捏造することも可能ということであり、それは兵庫にももちろん長福丸のためにもならないというのでした。
こうした展開は物語としての展開をリアリティーあるものに仕上げると同時に、物語の中の兵庫の人生を過酷なものとすることにも繋がります。
実際、物語は家重の影の人として徹底する忠光の人生をも描き出していくことになります。
こうして、家重は彼の本当の人柄、能力を正当に評価する人たちに支えられ、将軍として生きていくことになるのです。
そんな中で、老中の酒井忠音など家重に味方する人たちも現れてきます。
他方、小便を垂れ流す将軍など受け入れられず、家重にはその聡明さで知られる弟の宗武の方が将軍に相応しいとして、長福丸の廃嫡を画策する一派もあり、そこに松平乗邑などの名が挙げられることになります。
ただ、本書『まいまいつぶろ』では人間のあり方が善に偏っているように思われます。人の善性に重きを置いて描いてあるからこそ本書での家重は自身の障害を乗り越えて幸せの中に生きていくことができたと思われるのです。
例えば、家重の妻となった比宮との仲の描き方も、比宮という女性が、家重の本性を見抜く慈愛に満ちた女性として描かれているからこその物語でしょう。
この点に関しては、作者自らが「本作は、家重と忠光によって善の側に引き込まれる人々を描いた物語である。
」と書かれています( 好書好日 : 参照 )。
また、物語の途中で突然に御庭番の万里なる人物が登場したり、その後も他の会話の中で突然と万里の名が出てきたりすることがあります。
そのため、ときにその場面の視点の主を見失いかねない箇所が何か所かありましたが、これは読み手の私が未熟だからというだけではないでしょう。
とはいえ、こうした人物を設けることで、将軍徳川吉宗に特別な視座を与えることができ、物語のストーリー展開がやりやすくなったのだと思われます。
また、この万里という人物に関しては本書の続編として『まいまいつぶろ 御庭番耳目抄』という作品が刊行されており、作者もこの人物については重きを置いていることが伺われるのです。
本書『まいまいつぶろ』については、正直なところ、描かれている人物たちが出来すぎという気がしないでもありません。
しかしながら、そうした人々に支えられて将軍職を生きた家重、またその家重を支えた大岡忠光という人達を通して描かれる人間の善性の物語に浸るのもいいものでした。