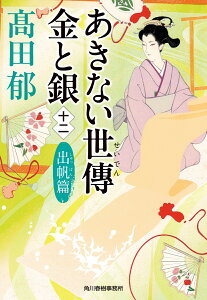『契り橋 あきない世傳 金と銀 特別巻(上) 』とは
本書『契り橋 あきない世傳 金と銀 特別巻』は『あきない世傳 金と銀シリーズ』の番外編上巻で、2023年8月に角川春樹事務所の時代小説文庫から320頁の文庫として書き下ろされた短編時代小説集です。
『あきない世傳 金と銀シリーズ』の登場人物のシリーズ本編では描かれていない新たな姿を知ることができる作品集です。
『契り橋 あきない世傳 金と銀 特別巻(上) 』の簡単なあらすじ
シリーズを彩ったさまざまな登場人物たちのうち、四人を各編の主役に据えた短編集。
五鈴屋を出奔した惣次が、如何にして井筒屋三代目保晴となったのかを描いた「風を抱く」。
生真面目な佐助の、恋の今昔に纏わる「はた結び」。
老いを自覚し、どう生きるか悩むお竹の「百代の過客」。
あのひとに対する、賢輔の長きに亘る秘めた想いの行方を描く「契り橋」。
商い一筋、ひたむきに懸命に生きてきたひとびとの、切なくとも幸せに至る物語の開幕。
まずは上巻の登場です!(上巻:内容紹介(出版社より))
『契り橋 あきない世傳 金と銀 特別巻(上) 』の感想
本書『契り橋 あきない世傳 金と銀 特別巻(上) 』は、それぞれに主人公を異にする四編の短編からなる作品集です。
まず「第一話 風を抱く」は、五代目の五鈴屋店主であり、幸の前夫であった惣次を主人公にした物語です。
その惣次は、本『あきない世傳金と銀 シリーズ』本編では本両替商「井筒屋」三代目保晴として再登場しますが、惣次の失踪から三代目保晴として登場するまでの空白の時を埋める物語です。
五鈴屋が江戸へと進出し、大きな壁にその行く手を遮られたとき、どこからともなく幸の前に現れてしてくれたさりげない助言や、その窮地からの脱出に手を貸してくれた惣次は、如何にして現在の地位を得たのかが明らかになります。
次の「第二話 はた結び」は、シリーズ本編で五鈴屋江戸本店で支配人を務める佐助を主人公にした物語です。
ある日佐助の目の前に、佐助と二世を誓い、十七年前に行方不明となったさよによく似た娘が現れますが、その娘はさよの妹だったのです。
五鈴屋江戸店の支配人佐助の恋心を描いた掌編です。
そして「第三話 百代の過客」は、本『あきない世傳金と銀 シリーズ』本編の当初から登場してきている五鈴屋の女衆で、今では小頭役となっているお竹を主人公とする物語です。
五鈴屋に奉公しておよそ六十年。江戸に出て来てからだけでも十八年になるお竹でしたが、近江屋支配人の久助が郷里へ帰るのに伴い、一度大坂へと帰省するかどうか悩んでしました。
「第四話 契り橋」は、「五鈴屋の要石」と呼ばれた治兵衛の一人息子で、型染めの図案を担当しヒット商品を送り出すなど、五鈴屋江戸店の発展に大いに寄与した賢輔の物語です。
この賢輔は、次の五鈴屋店主久代目徳兵衛をつくことになっている人物でもありますが、密かに抱いている女主人の幸への想いの行方が気になる存在でもあります。
本当は、この話の後の二人の消息を知りたいのですが、その話は書かれるときが来るのでしょうか。それとも、もしかしたら本書に続く下巻でその一端でも明かされるのでしょうか。
以上のように、本書『契り橋 あきない世傳 金と銀 特別巻(上) 』では、惣次、佐助、お竹、賢輔の四人が物語の中心となっています。
また本書は既に終わってしまったシリーズのスピンオフ作品ではありますが、本編シリーズが非常に人気の高いベストセラーシリーズであったため、本編では語られていなかった様々な事柄を追加で書かれたものでしょうか。
本編中では語られてこなかった事情や、本編終了後の登場人物たちの消息などが、高田郁の丁寧な筆致で紡がれていきます。
本シリーズのファンにとっては、もう読めないと思っていたシリーズ作品を再び読むことができるのですから喜びもひとしおです。
本『あきない世傳金と銀 シリーズ』はシリーズの番外編であるため、本書だけを読んでも当然のことですがその意味が分かりにくい作品です。
ですが、既に終了してしまった本『あきない世傳金と銀 シリーズ』本編の間隙を埋める作品であり、続編が読めないシリーズの淋しさを埋めてくれる作品でもあります。
本編の『あきない世傳金と銀 シリーズ』が好評のうちに終わってしまったのは非常に残念なことではあるのですが、こうしてスピンオフ作品として提供してくれるのはまた楽しみでもあります。
今後、このような形でもいいので、本シリーズが紡がれていくことを願いたいものです。