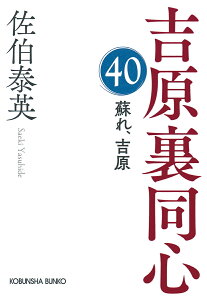『恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(二十六)』とは
本書『恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(二十六)』は『新・酔いどれ小籐次シリーズ』の第26弾で、2024年1月に文庫書き下ろしで出版された長編の痛快時代小説です。
一旦は終了したはずの『新・酔いどれ小籐次シリーズ』が、赤目駿太郎の剣術家としての成長と淡い恋を書きたいとの思いから再開した、と作者自身のあとがきにありましたが、ハードルが上がっただけに若干期待とは違った印象でした。
『恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(二十六)』の簡単なあらすじ
江戸・三十間堀の小さな町道場が、怪しい証文を盾にした男たちから狙われている。道場主と孫娘の愛を救うため、十八歳の駿太郎は名を秘して入門する。親分や読売屋と協力して活躍する息子を見守るおりょう、隠居を考える小籐次。しかし親子への挑戦状がー伊勢まいりが大流行する中、あの鼠小僧も登場!?恋と勝負と涙の感動作。(「BOOK」データベースより)
序章
第一章 細やかな町道場
湯屋にいる小籐次と駿太郎のもとに、難波橋の秀次親分がある道場の難題を相談に来た。その道場の加古李兵衛正高とその孫娘の愛のもとに、愛が幼い頃に出奔した父親の署名がある借用書を持って夢想谷三兄弟が道場の沽券を渡せとやってきたというのだった。
第二章 もうひとりの娘
加古道場で稽古をするようになった駿太郎が、加古正行と愛の二人を望外山荘へと連れてきた。すると、愛は駿太郎の新しい姉となり、またおりょうの娘となり、新しく望外山荘に住むこととなった薫子を姉と呼ぶようになるのだった。
第三章 お手当一両二分
師走のある日、小籐次親子が研ぎの仕事を終え帰る途中、竹屋の渡しの近くで浪人者からある姫君と奉公の女中の娘を助けた。また大晦日の大雪のため二人が川向うを見廻りに行くと、ある奇妙な一団が久慈屋に押し入ろうとするところに出会った。
第四章 新春初仕事
年の瀬から降り始めた雪のため稽古ができなくなった駿太郎は、望外山荘に近にある越後長岡藩の抱屋敷にある道場で稽古を願うことを思いつく。その後正月六日になり、望外山荘きた桃井春蔵が、十一日の桃井道場での具足開きに来てくれと言ってきた。
第五章 愛の活躍
小籐次親子が久慈屋店先での研ぎ仕事をしていると、夢想谷三兄弟が加古道場に訪れるとの空蔵からの伝言があった。日時は明記してなかったらしく、正月半ばを過ぎても、空蔵がいろいろと仕掛けでも一向に姿を見せないのだった。
あとがき
『恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(二十六)』の感想
本書『恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(二十六)』は、一旦は終わりを迎えた『酔いどれ小籐次留書シリーズ』でしたが、作者の希望により再開されることになったシリーズ二十六巻目の作品です。
かなりの期待をもってさっそく読んでみたのですが、期待が高すぎてハードルが上がったためか、今一つという印象に終わってしまいました。
駿太郎の淡い恋を描きたいとの作者の意向があっての再会だそうですが、本書では新しく二人の娘が登場します。
一人は加古李兵衛道場の孫娘の愛であり、もう一人は望外山荘近くに住む片桐家の十四歳の娘の麗衣子です。
一人目の愛については、駿太郎がすぐに姉と呼び始めたので不思議に思っていると、今度は麗衣子という娘が突然に登場します。
それも前後の脈絡もなく何の背景の説明もない浪人者に攫われそうになっている娘を助けたことが知り合うきっかけです。
この出会いは物語のストーリーとは何の脈絡もなく突然の登場であるため、どうにもあまりに突然すぎて単なるご都合主義としか思えず、違和感しかありません。
とはいえ、この頃の佐伯泰英 作品はそうしたストーリーの進行とは無関係な登場人物がしばしば登場することがあり、そういう意味ではあまり驚きはないとも言えそうです。
ただストーリー展開とは関係のない人物の登場が多いとは言っても、それは単なる賑やかし的な浪人者やチンピラなどが主であり、今回のようなストーリー上重要な位置を占める人物については無かったことと思います。
また、愛の実家である加古李兵衛道場に押しかけてきた夢想谷三兄弟にしても、愛の父親である加古卜全正行の直筆と思われる二百九十両の借用証を持参しての押しかけですから、そのままに道場の土地と敷地の沽券状を取得できたと思われるのです。
それをわざわざ自分たちと加古道場の沽券状をかけて尋常の勝負を願ってくるのですから妙な話です。
このような展開は物語のリアリティを欠く展開としか言えず、読者の作品に対する感情移入を妨げるだけだと思います。というよりも私にとってはそうなのです。
せっかく一旦はシリーズ終了宣言したものを撤回するのですから、もう少しこうした点の物語の運びを考えて欲しいと思ってしまいました。