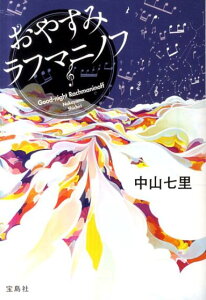『いまこそガーシュウィン』とは
本書『いまこそガーシュウィン』は『岬洋介シリーズ』の第八弾で、2023年9月に288頁のハードカバーで宝島社から刊行された長編の推理小説です。
激化する人種差別抗議運動を前に分断するアメリカで音楽の力を示すことができるか、をメインテーマにしたサスペンス作品です。
『いまこそガーシュウィン』の簡単なあらすじ
電子書籍限定にて連載した『このミステリーがすごい! 中山七里「いまこそガーシュウィン」vol.1~4』、待望の書籍化です! アメリカで指折りのピアニストであるエドワードは、大統領選挙により人種差別がエスカレートし、変貌しつつある国内の様子を憂いていた。そこで、3ヵ月後にカーネギーホールで開催予定のコンサートの演目に、黒人音楽をルーツにもつジョージ・ガーシュウィン作曲の「ラプソディ・イン・ブルー」の演奏を希望。6年前のショパン・コンクール中、5分間の演奏で人命を救った男・岬洋介との共演も決まり、期待に胸を膨らませる。岬と共演することで、大統領夫妻もお忍びで鑑賞に来ることが決まり、エドワードと岬は練習に励む。一方その頃、大統領暗殺の依頼を受け、計画を進めていた〈愛国者〉は、依頼主の男から思わぬ提案をされーー。音楽の殿堂、カーネギーホールで流れるのは、憎しみ合う血か、感動の涙か。どんでん返しの帝王が放つ、累計168万部突破の音楽シリーズ最新刊!(内容紹介(出版社より))
『いまこそガーシュウィン』の感想
本書『いまこそガーシュウィン』はミステリーと謳ってある作品ではありますが、ミステリーというよりはサスペンス小説と言った方さよさそうな作品でした。
本書ではミステリーとして提示された謎というほどの謎はなく、ただ、暗殺者である「愛国者」の正体は誰か、というくらいが謎といえるものであり、その謎ですらも決して本筋ではありません。
本筋は、語り手であるエドワードとシリーズの主人公である岬洋介とのジョイントコンサートの行方、つまりはこのコンサートでの暗殺者の大統領暗殺という仕事の行方がどうなるのかという点にあるのです。
ところで、あくまで商業ベースとしてのコンサートを見る時、「ラプソディー・イン・ブルー」という楽曲ではお客を呼べないというエドワードのマネージャーの意見があります。
この点に関しては、「ラプソディー・イン・ブルー」といえば人気の楽曲であるのに客を呼べないのか、という疑問しかない私としては、素人にはそこらの感覚は分からないのだろうと思うだけです。
ともあれ、マネージャーのそういう意見があったればこそ、岬洋介とのジョイントコンサートが開催されることになったのですから、それはそれでよしとすべきなのでしょう。
本書の本筋はジョイントコンサートの行方だとしても、本書の魅力を考えるときは、まずは中心となる二人が音楽の持つ力を信じていることだと思われます。
つまり、トランプ元大統領(2024年3月現在)を思わせる人種差別主義者のアメリカ大統領がもたらしたアメリカの分断という現状を、岬洋介とエドワードという二人のピアニストの競演でいくらかなりとも和ませることができるのではないかということです。
次に、「音楽」という芸術の有する影響力を前提にしての話ですが、「ラプソディー・イン・ブルー」という楽曲のもつ魅力があります。
そして本書には「ラプソディー・イン・ブルー」とい楽曲の歴史、ジョージ・ガーシュインという大作曲家の一番高名ともいえる楽曲のもつ背景が詳しく解説してあります。
そこらは実際読んでもらうしかありません。
ちなみに、本書ではエドワードと岬洋介とのジョイントコンサートの様子が描かれていて、そもそも「ラプソディー・イン・ブルー」という楽曲が「二台のピアノを前提として察刻されたという説明がなされていますが、ウィキペディアでも「ガーシュウィンが2台のピアノ用に作曲したもの」だと記載してありました( ウィキペディア : 参照 )
本書の魅力の第三は、作者の中山七里が作り出した岬洋介というキャラクターの魅力と、音楽の魅力を文章で示すという作者の表現力だと思います。
この点は本書の魅力と言うよりは本『岬洋介シリーズ』の魅力と言うべきであり、だからこそ帯にあるようなシリーズ累計160万部という人気シリーズになっているのでしょう。
さらには、ミステリーシリーズ、サスペンス小説としての本書の魅力があることももちろんの話です。
ただ、これまで書いてきたこととは矛盾するようですが、本書は中山七里という作家の作品の中では決して突出した作品とは言えないと思います。
それはジョイントコンサートの成功と大統領暗殺というサスペンスの点が弱いと感じてしまったからですが、それでもなお平均的な面白さを持っていると思います。
この頃あまりこの作者の作品を読んでこなかったので、あらためてまた読み始めようかと思います。その程度には面白さを感じた作品だったということでしょう。