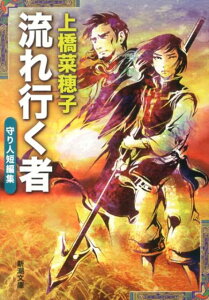『レーエンデ国物語 4 夜明け前』とは
本書『レーエンデ国物語 4 夜明け前』は『レーエンデ国物語シリーズ』の第四弾で、2024年4月に600頁のハードカバーで講談社から刊行された長編のファンタジー小説です。
個人的好みからいうと、これまでの物語の流れからして今回は今一つの展開でした。
『レーエンデ国物語 4 夜明け前』の簡単なあらすじ
四大名家の嫡男・レオナルドは佳き少年だった。生まれよく心根よく聡明な彼は旧市街の夏祭りに繰り出し、街の熱気のなか劇場の少女と出会う。-そして真実を知り、一族が有する銀夢草の畑を焼き払った。権力が生む欺瞞に失望した彼の前に現れたのは、片脚をなくした異母妹・ルクレツィアだった。孤島城におわす不死の御子、一面に咲き誇る銀夢草、弾を込められた長銃。夜明け前が一番暗い、だがそれは希望へと繋がる。兄妹は互いを愛していた。きっと、最期のときまで。(「BOOK」データベースより)
『レーエンデ国物語 4 夜明け前』の感想
本書『レーエンデ国物語 4 夜明け前』は『レーエンデ国物語シリーズ』の第四弾の長編のファンタジー小説です。
これまでのシリーズ作品と照らしても意外な展開を見せ、またこれまで貼られた伏線を回収する作業に入っている作品でもあります。
ただ、個人的にはファンタジー物語としてそれなりの魅力は感じたものの、総じて本書の展開に対しては疑問符のつく作品でした。
その疑問符について詳しく述べることは本書のネタバレをすることになりますので実際読んでいただくことしかできません。
ただ、主役の一人であるルクレツィア・ペスタロッチの行動が納得のいかないものだった、個人の行動としてではなく、物語の展開として認めることができなかった、ということだけ記すにとどめておきます。
本書の主人公は一人は父ヴァスコと母イザベルとの間のレオナルド・ペスタロッチで、もう一人はレオナルドの異母妹のルクレツィア・ペスタロッチです。
九十年ほど前、聖イジョルニ帝国は始祖ライヒ・イジョルニの血を引いた五大名家のうち現在も残っているペスタロッチ家やダンブロシオ家などの四大名家で聖イジョルニ帝国を教区分割統治することになりました。
そのあと、四大名家のうちでも最弱の家柄だったペスタロッチ家がヴァスコなどの活躍で力を得、次期法皇帝になろうかというほどの力を得ていきます。
ヴァスコの息子で主人公であるレオナルドはペスタロッチ家の次期当主となるべき立場でした。
このレオナルドの友人だったのが、一人はペスタロッチ家の忠臣ジュード・ホーツェルの息子のブルーノであり、もうひとりがアリーナを母とするレオナルドの二つ年下の従兄弟のステファノ・ペスタロッチでした。
レオナルドとブルーノはポネッティ旧市街へイジョルニ人であることを隠して遊びに行き、「春光亭」のレオーネと知り合い、レーエンデ国物語 喝采か沈黙かで登場してきたリーアン・ランベール作の戯曲「月と太陽」と出会います。
そんな中、レオナルドの家に義母妹であるルクレツィア・ペスタロッチがやってくるのでした。
本書で作者が述べたいことは「正義」の衝突ということでしょう。
「正義」という観念は相対的なものであり、「正義」を主張する者の数だけ「正義」がある、とはよく言われることです。
それは今現在の現実社会で起きている戦争を見ればすぐにわかることで、どちらの側も自分の国の正義を主張した結果起きていることです。
作者は「普遍的な正しさは、僕ら人間には荷が重すぎるね」と新聞記者のビョルンという人物に言わせていますが、それは皆が感じていることだと思われます。
先に述べたように、本書に対する私の感想としては、疑問符がつく作品だったというにつきます。
本書でのルクレツィアの仕業は常軌を逸しているというレベルを超えており、本書中でも言われているように、ほかに手段があるだろうと思うからです。
物語としては確かに面白く、それなりに惹き込まれて一気に読み終えたのですが、私の好きなファンタジー作家の上橋菜穂子などの作品と比べるとどうしても上橋作品に軍配を上げてしまいます。
何故かよく分かりませんが、それは多分物語の組み立て方が上橋作品の方が緻密な印象を受け、物語世界の完成度が高い印象なのです。
つまりは、上橋作品は戦術や戦略面での視点や、国家間の地政学的な視点まで加味されていたりと、読者が気づかないであろう細かなところまで考えられていて読んでいてその視野の広さに引き込まれるのです。
その点田崎作品はストーリー展開の面白さはあるものの、上橋作品に比して視野の広さ、心象描写細かさにおいて今一つ及ばない気がします。
他の作家さんと比較するなど失礼かと思いますが、要は私の好みとして少し異なるのだ、ということです。
ですから、華やかなファンタジーものを好む方には本書のストーリー展開には胸躍るものがあり、かなり評価が高くなるのではないでしょうか。
でも、これまで文句を言ってきた私も最終巻となる次巻『レーエンデ国物語 海へ』を心待ちにしているのですから勝手です。
自分のことではあるもののやはり読み手は我儘だと思いますが、しかし正直なところです。