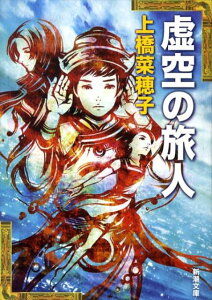『蒼路の旅人』とは
本書『蒼路の旅人』は『守り人シリーズ』の第六弾で、2005年04月に偕成社からハードカバーで刊行され、2010年8月に新潮文庫から著者のあとがきと大森望氏の解説まで入れて380頁の文庫として出版された、長編のファンタジー小説です。
チャグムが主人公の作品としては『虚空の旅人』に続く作品であり、国家間の思惑なども加味された新たにダイナミックに展開される物語としてバルサの話とはまた違った面白さを持った作品となっています。
『蒼路の旅人』の簡単なあらすじ
生気溢れる若者に成長したチャグム皇太子は、祖父を助けるために、罠と知りつつ大海原に飛びだしていく。迫り来るタルシュ帝国の大波、海の王国サンガルの苦闘。遙か南の大陸へ、チャグムの旅が、いま始まる!-幼い日、バルサに救われた命を賭け、己の身ひとつで大国に対峙し、運命を切り拓こうとするチャグムが選んだ道とは?壮大な大河物語の結末へと動き始めるシリーズ第6作。(「BOOK」データベースより)
『蒼路の旅人』の感想
本書『蒼路の旅人』では、チャグムが主人公となってタルシュ帝国を舞台として冒険物語が繰り広げられます。
これまで、バルサが主人公の作品では「新ヨゴ国」(『精霊の守り人』『夢の守り人』)、「カンバル王国」(『闇の守り人』)、「ロタ王国」(『神の守り人』)が、またチャグムが主人公の作品としては「サンガル王国」(『虚空の旅人』)がそれぞれに物語の舞台として設定されていました。
そしてバルサが主人公の場合は、舞台となっている土地に伝わる伝説と異世界との絡みを中心に、短槍使いのバルサならではの活劇を絡めた物語として構成されていました。
一方、チャグムが主人公の物語では、新ヨゴ皇国の皇子としてのチャグムという立場に応じた国家間の対立を前提とした構成になっています。
そして本書は『虚空の旅人』の続編として、今後の国家間の争いを前にしてのタルシュ帝国が舞台になっているのです。
本書『蒼路の旅人』では、サンガル王国からの援軍の要請に対し、チャグムの祖父の海軍大提督トーサに主力軍の三割ほどの艦隊を任せ派遣するという帝の決定に反対し帝の怒りを買ったチャグムは、トーサと共に出陣することを命じられます。
チャグムには護衛兵として<帝の盾>で別名<狩人>と呼ばれる暗殺者のジンやユンが同行しており、帝のチャグムへの決別の意思を見ることができるのでした。
本書でのチャグムは、父王の怒りをかった結果従軍することになりますが、サンガル軍にとらわれた後、チャグムの父である帝の命によりチャグム暗殺の任を担っているジンの助けを得てサンガル軍から脱出した後が本来の物語に入ります。
というのも、チャグムはタルシュ帝国の密偵であるアラユタン・ヒュウゴに捕らわれ、タルシュ帝国の実情をその目で見ることになるのです。
このヒュウゴという人物が本書での要となる人物であり、新ヨゴ皇国の母国でもあるタルシュ帝国の枝国となった元ヨゴ皇国の出身だったのです。
チャグムはこの虜囚となった経験により、タルシュ帝国の枝国となることの意味を思い知らされ、同時に新ヨゴ皇国の存続、新ヨゴ皇国の民の平和な生活のためには現在の帝、即ちチャグムの父が如何に障害になっているかをも思い知らされるのです。
こうしてチャグムが虜囚となっている間に、タルシュ帝国のハザールとラウルという二人の皇子、それにラウル皇子に仕えるヒュウゴの話などを通して、ものの見方の多様性などを学んでいきます。
つまりは、読者は著者上橋菜穂子の「歴史には絶対の視点などなく、関わった人の数だけ視点があり、物語がある。」(文庫版あとがき「蒼い路」:参照)という視点が明確に示されていることに理解が及びます。
ただ、新ヨゴ皇国の民の幸せに帝がいかに障害となっているかを思い知らされたチャグムの決断は哀しみに満ち溢れたものにならざるを得ません。
本シリーズは個人の視点が主になるバルサの物語と、ダイナミックな国家間の物語が描かれるチャグムの物語とではかなりその色合いを異にします。
その二つの物語が合流することになる『天と地の守り人』はどのような物語になるのか、楽しみでなりません。