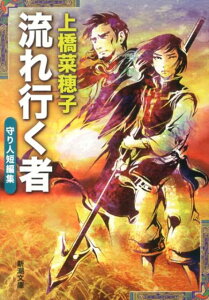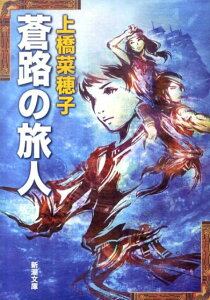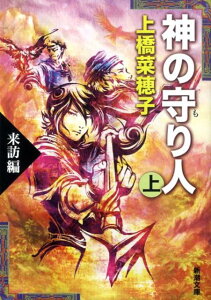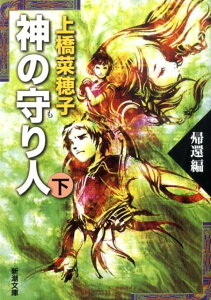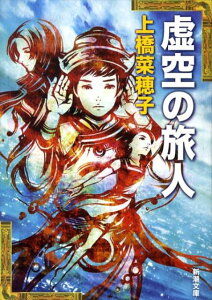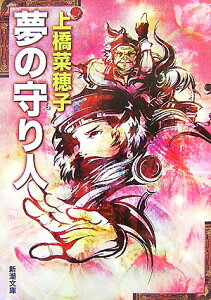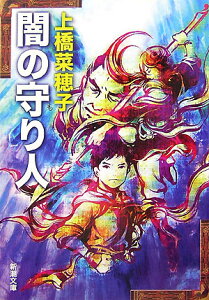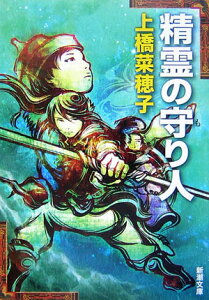『香君』とは
本書『香君』は、2022年3月に上・下二巻として刊行された、上下巻合わせて900頁弱の長編のファンタジー小説です。
『鹿の王』で本屋大賞を受賞した著者上橋菜穂子による新たな冒険への旅立ちの書であり、非常に興味深く読んだ作品です。
『香君』の簡単なあらすじ
遥か昔、神郷からもたらされたという奇跡の稲、オアレ稲。ウマール人はこの稲をもちいて帝国を作り上げた。この奇跡の稲をもたらし、香りで万象を知るという活神“香君”の庇護のもと、帝国は発展を続けてきたが、あるとき、オアレ稲に虫害が発生してしまう。時を同じくして、ひとりの少女が帝都にやってきた。人並外れた嗅覚をもつ少女アイシャは、やがて、オアレ稲に秘められた謎と向き合っていくことになる。( 上巻 : 「BOOK」データベースより)
「飢えの雲、天を覆い、地は枯れ果て、人の口に入るものなし」-かつて皇祖が口にしたというその言葉が現実のものとなり、次々と災いの連鎖が起きていくなかで、アイシャは、仲間たちとともに、必死に飢餓を回避しようとするのだが…。オアレ稲の呼び声、それに応えて飛来するもの。異郷から風が吹くとき、アイシャたちの運命は大きく動きはじめる。( 下巻 : 「BOOK」データベースより)
ウマール帝国から帝国支配下の西カンタル藩王国に視察官として派遣されていたマシュウは、西カンタル藩王国のかつての国王だったケルアーンの孫娘であるアイシャとその弟のミルチャを捉えた。
現西カンタル藩王国ヂュークチの前に連れ出されたアイシャは殺される運命を受け入れていたものの、彼女が有する優れた嗅覚により目の前にいる国王が毒殺されようとしている事実を指摘するのだった。
またアイシャはその嗅覚によって自分たちに出された飲み物に毒が入っていることに気付いたものの、そのまま飲み物を飲み干し埋葬されてしまう。
しかし、アイシャ兄弟は毒薬入りの飲み物を飲んだにもかかわらず、マシュウ=カシュガによって助けられたのだった。
『香君』の感想
著者上橋菜穂子が、2015年度の本屋大賞と日本医療小説大賞をダブル受賞した『鹿の王』の次に出版されたファンタジー小説です。
本書『香君』は、「香り」に焦点を当て、特別な嗅覚をもつ者を主人公としたこれまでにない視点の物語です。
そうした独特な視点のこの物語世界には「香君」という活神の制度があり、帝国国王とは別に国民の信頼を集めています。
この「香君」という制度では、活神の身体が老いると<再来の年>にお告げの場所で十三歳になった新しい香君を見つけるといい、それはまるでチベットにおけるダライ・ラマの制度のようでもあります( 14世ダライ・ラマ法王発見の経緯と輪廻転生制度 : 参照 )。
本書『香君』のようないわゆるファンタジーと呼ばれる作品は、殆どの場合はその世界観がそれなりに構築されていて物語を違和感なく読むことができます。
しかし、本書の著者上橋菜穂子が描く作品のように物語世界丁寧に描かれている作品はそうはないと思います。
例えば三部作が映画化もされたファンタジーの名作中の名作である『指輪物語』は分かり易い例の一つでしょう。
他に日本の作品でいえば『図書館の魔女シリーズ』などの 高田大介の作品が挙げられると思います。
こうした作品は物語の世界がその世界としてきちんと作り上げられているからこそ、その世界のリアルさを表現していることができていると思うのです。
そうしたなかでも上橋菜穂子の描く作品は物語の世界が丁寧に構築してあり、この世界の政治体制や権力のありようが苦労することなく頭に入ってきます。
そのことは上記の『鹿の王』にしても、また本書『香君』においても当てはまり、ウマール帝国を中心とする政治体制とそこに存在する「藩王国」との関係、それに「香君」という特殊な制度の在りようが物語の前提として理解できるのです。
そうした前提は、この丁寧に構築された世界で「香君」が存在する理由も、主人公が冒頭から殺されそうになりつつも、その後の目まぐるしく身分が変転する理由を理解することが容易になります。
本書『香君』の魅力はその物語世界の正確性と同時に、上記の「香君」という存在の設定でしょう。
特別な「嗅覚」という能力を持つ者を主人公に据えるという他にはない発想で綴られたこの物語は、作者により丁寧に構築された物語世界のうまさと相まって、読む者に多くの期待を抱かせる作品です。
読んでいる途中では特殊能力を持つ主人公の設定が先にあって、その能力に合わせた世界を考えたのかと思っていたのですが違いました。
作者によるあとがきを読むと、優れた嗅覚を持つ者を主人公としたのではなく、植物や虫が発する香りについての知見が先にあり、その微細な香りをも嗅ぐことのできる能力を有する者という設定ができたのだそうです。
そうした設定の中に設けられた「オアレ稲」という物語の道具がまたよく考えられていて、本書の魅力の構築に役立っています。
適当な配合、そして量で作られた秘伝の肥料を与えることを前提に、暑さにも寒さにも、また害虫にも強いという性質をもつこの植物は、その性質のために帝国の存立基盤ともなっている植物なのです。
この「香君」と「オアレ稲」の存在とがこの物語の核であり、サスペンスフルな物語展開の骨子となっています。
つまり、オアレ稲は民を豊かにはしたものの、他の作物が育たなくなるという欠点を有しており、さらには特別な肥料が必要特性も有し、帝国の支配の道具としてうってつけの存在だったのです。
こうした作物は戦略的な意義を有していて、私達の現実世界を意識した寓意的な物語ではないかと考えてしまいます。
そんな生々しい現実世界の情勢を背景に垣間見ることのできる本書の物語は、それでもアイシャという少女と香君の存在により、未来を見据え、力強く生きていくことを示してくれています。
切れ者の大人たちの謀りごとを前に、ただ卓越した嗅覚を持つ少女がその能力をフルに生かして皆の幸せを祈り、そして行動していく話ですがその未来への展望が見事です。
著者上橋菜穂子の作品では、心に残る言葉が記されていますが、本書においてもそれは変わりません。
自然の摂理は確かに無情だけれど、でも、けっこう公平なものだとか、人には知識や経験から推論を導き、考え、希望を見出す力がある、などというアリキ師の言葉などそうでしょう。
生き物は自分ではどのような存在に生まれるかは選べないが、どんな小さな者も己の役割を担って生きている、などという「香君」オリエの言葉などもそうです。
こうした言葉が本書のあちこちにちりばめられています、だからといって、本書が難しく高尚な言葉を語っているということではありません。
まさにファンタジーとして読みやすい物語のなかに必然的な言葉として散りばめられているのであって、普通に読んでいるままに頭に入ってきます。
ただ、本書『香君』は、著者上橋菜穂子の『鹿の王』のような元気のいいアクションの場面はありません。相手は言葉を持たず動くこともない植物であり、人間同士の戦いの場面もありません。
虫との戦いはありますが、彼らも単に本能に従って食べ物を探すだけです。
植物の発する「香り」が主人公のアイシャには、ときには嬉しく、ときには騒がしく「聞こえる」のです。
その植物の香りをもとに推測し、考え、行動するアイシャの姿はアクション場面こそないものの心動かされます。
この点の発想は、多分ですが、日本文化の一つとしてある、香りと出会い向き合う「香道」の「聞く」という言葉から発想されているのでしょう( 香りと出会い、向き合う。聞香・お香の楽しみ方 : 参照 )。
でも、そうしたことはどうでもよく、単純に本書『香君』という物語に身を委ね、物語を楽しめばいい、と心から思います。
それほどに面白く、よく考えられた物語です。