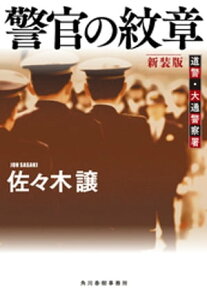『警官の酒場』とは
本書『警官の酒場』は『北海道警察シリーズ』の第十一弾作品で、2024年2月に416頁のハードカバーで角川春樹事務所から刊行された長編の警察小説です。
本書をもってこのシリーズも終わると聞いていて残念に思っていたのですが、実際は第一シーズンが終わるということで一安心しているところです。
『警官の酒場』の簡単なあらすじ
捜査の第一線から外され続けた佐伯宏一。重大事案の検挙実績で道警一だった。その佐伯は、度重なる警部昇進試験受験の説得に心が揺れていた。その頃、競走馬の育成牧場に強盗に入った四人は計画とは異なり、家人を撲殺してしまう。“強盗殺人犯”となった男たちは札幌方面に逃走を図る…。それぞれの願いや思惑がひとつに収束し、警官の酒場にある想いが満ちていくー。大ベストセラー道警シリーズ、第1シーズン完!それぞれの季節、それぞれの決断ー。(「BOOK」データベースより)
大通警察署生活安全課の小島百合は、スマホを奪われたという女子高校生についての報告書を読んでいるときに、女性の緊急避難所を開設しているボランティアグループの山崎美知から暴力団風の男たちから嫌がらせを受けていると連絡があった。
佐伯宏一は、近頃認知症の兆候を見せてきている父親の身を案じながらも上司と共に刑事部長から警部昇任試験についての話を聞いていたが、直ぐに設備業者のワゴン車の盗難事件発生を告げられた。
津久井卓巡査部長と滝本浩樹巡査長は人質立てこもり事件を解決した後、競走馬の育成牧場での強盗殺人事件についての連絡を受けていた。
『警官の酒場』の感想
本書『警官の酒場』は『北海道警察シリーズ』の第十一巻となる作品で、本作品をもって第一シーズンが終わるそうです。
まずはシリーズ自体は継続するということで安心しましたが、本書の終わり方が終わり方なので、今後の展開がどうなるものか期待が膨らむばかりです。
本書でも例によって佐伯宏一警部補、津久井卓巡査部長、小島百合巡査部長という三人の警察官のそれぞれが別事件を追いかけています。
でも、佐伯の部下であり相方でもある新宮昌樹巡査も第一話からの佐伯のコンビとして登場していますので、新宮巡査も加えて四人の物語といった方がいいのでしょう。
本書では、佐伯宏一と新宮昌樹のコンビは古いワゴン車の盗難事件を、津久井卓は闇バイト問題が絡んだ競走馬育成牧場での強盗殺人事件を、そして小島百合は女子高生のスマホ盗難事件を担当しています。
これらの事件を捜査するなかで得られた細かな情報が、互いに認識しないままに関連してくる様子が、読者にはよく分かるように物語が進行していくのはこのシリーズのいつものパターンです。
いつものパターンではあってもマンネリ化に陥ることはなく、それぞれの捜査の丁寧な描写は物語の展開にリアリティを与えています。
またそれと共に、サスペンス感に満ちているのはやはり作者の筆力の為すところだと思われます。
このように、本書『警官の酒場』のストーリーも本シリーズのパターンに則った運びですが、もう一つの本シリーズの特徴である、時事的な事柄を物語に織り込んでいるという点もまたあてはまります。
それは「闇バイト」の問題であり、一面識もない連中が高額報酬に惹かれて当該強盗事案のためにだけ集まり、犯行を遂げるというものです。
しかし、公にできない金があるはずの競走馬育成牧場に押し入るだけの犯行の筈が、気の短い仲間の一人が予想外の行動に出て被害者を殺してしまい、機動捜査隊の隊員である津久井卓巡査部長がこの強盗殺人事件を追いかけることになります。
この闇バイトに集まった個々人の描写もその心の動きまで丁寧に押さえてあるところなど、このシリーズがリアリティに満ちている理由がよく分かります。
また、本書『警官の酒場』はシリーズの第一シーズンの終わりということで、中心となる四人それぞれの今後が示唆されています。
そのことは作者の佐々木譲自身がこの北海道警察シリーズの生みの親でもある角川春樹との対談の中で、「それぞれの個人史としても区切りがつけられたのではないか
」と語っていることでもあり、意外といってもいい展開になっています( Book Bang : 参照 )。
そのことは、遠くない未来に始まるはずの第二シーズンに大きな期待を抱かせることにもなっているのです。
津久井卓は今後の捜査にはどうかかわるのか、小島と佐伯の二人の行く末はどうなるのか、そして佐伯の今後の身分は、そして何よりもこのシリーズの傾向はどうなるのか大いに期待させられます。
いまはただ続巻の刊行が待たれるばかりです。